梅子黄(うめのみきばむ) 七十二候の中で、芒種(ぼうしゅ)の末候にあたります。 青く大きく実った梅の実が黄…

2021.06.21 up
乃東枯(なつかれくさかるる)
乃東枯(なつかれくさかるる)
七十二候の中で、夏至(げし)の初候にあたります。
乃東(ウツボグサの古名)の花穂が黒ずんで枯れたように見える頃。
夏の「乃東枯(なつかれくさかるる)」と冬の冬至の初候「乃東生(なつかれくさしょうず)」が対になっています。 ※乃東生(なつかれくさしょうず 12月22~26日頃 乃東が芽を出し始める頃。)
冬至に芽を出し、夏至に枯れるという対を表しています。
ウツボグサ
5月~7月ごろに花をつけるシソ科の多年草。高さ30センチほどで日当たりの良い草原や道端で見かけることが出来ます。
紫色の花が花穂にいくつも咲き、この花穂が黒ずんだあとに乾燥させると「夏枯草(かごそう)」と呼ばれる生薬になります。煎じて飲むと利尿や消炎作用があると言われています。また煎液は腫れの塗り薬やうがい薬にもなります。
ウツボグサという和名は、花穂の形がかつて武士が使った矢を入れる容器の「靱(うつぼ)」に見立てたと言われています。
短夜(みじかよ)

夏至とは北半球では一年で一番昼間の時間が長く、夜が一番短い頃。冬至と比べると4時間以上昼間の時間が長くなります。
夏の昼間の時間が長い様子を「短夜(みじかよ)」、春は「日永(ひなが)」、秋は「夜長(よなが)」、冬は「日短(ひみじか)」。季語として古くから親しまれている日本の季節を表す趣ある表現です。
1年を72に区切って、季節を細かく分け、そのひとつひとつは気象の変化や動植物の様子を短い言葉で表現されています。『二十四節気』は半月ごとの季節の変化を示していますが、これをさらに分けて、5日ごとに区切って表したものを『七十二候』といいます。季節の変化を細かく見つめ、農作業に生かしていたようです。
意外と知らないカレンダーのあれこれ 教えて!めくろう君(七十二候について)
春夏秋冬の『四季』。立春から大寒までの『二十四節気』。そして、それをさらに細かく分けて表現した『七十二候』。言葉にはさまざまな意味が込められており、字面を見るだけでも季節を感じられそうです。
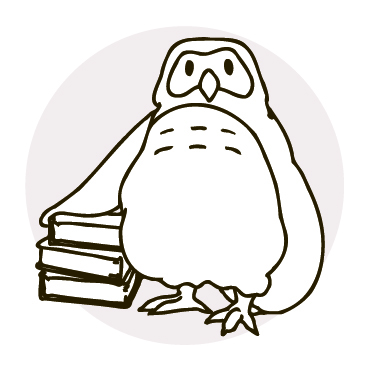
夏至を迎え昼間の時間が長く、植物たちも緑を生き生きと成長していく中、ウツボグサは枯れてしまうんだね。英名ではall-heal(すべてを治す)だよ!
めくろうくんのちょっと雑学!?
お買いもの
色彩暦(二十四節気入)
¥1,265(税込)
四季の移り変わりと共にある二十四節気、方位や時間、日々の吉凶を示す六曜など、日本の暦は365日、1日1日がそれぞれの意味を持っています。1日の大切さと四季折々の暮らしの節目を、暦の中で感じてください。12ヵ月のイメージを12色で伝える、使いやすいカレンダーです。
四季の移り変わりと共にある二十四節気、方位や時間、日々の吉凶を示す六曜など、日本の暦は365日、1日1日がそれぞれの意味を持っています。1日の大切さと四季折々の暮らしの節目を、暦の中で感じてください。12ヵ月のイメージを12色で伝える、使いやすいカレンダーです。








